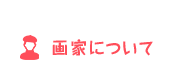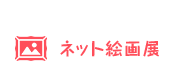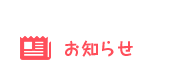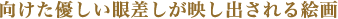
紹介されている絵画には、馬・犬・猫・風景・花・子供などが描かれています。彼の絵を見ていくうちに不思議なことに気づかされます。生きものの目がどれも優しいのです。これほどまでに慈愛に満ちた目は一体なんなのだろう…。そのことに思いを巡らせながらページをめくっていき、ところどころに挟み込まれている彼の人生に関わってきた人たちの言葉を読んでいて、はたと気づきました。牧野さんの人柄、つらいことを乗り越えて人に勇気を与えようとする温かい気持ち、彼はいつでもどんな時でも与えることを喜び、本当に多くの人に大切にされ愛されてきた人だと。動物に描かれている目は牧野さん自身の目なのではないか、自分に多くを与えてくれている人たちへの感謝の思いがそこに投影されているから返ってくる優しい目なのかもしれないと。
「午年生まれなんで馬が好きなんです」
馬を多く描いていることの理由を尋ねられたら、とりあえずそのように答えることにしている。それで、ほとんどの人は納得してくれるのだから不思議なものである。しかし、それで終わらせてしまうのでは稚拙に過ぎるから、勢いよく馳せる姿に、生命のエネルギー感を刻みつけたい。

静かに草を食む佇まいに、生きることの本質を封入したい。
仲睦まじい母仔の姿に、安らかで強い絆を紡ぎたい。
2002年の10月、北海道の牧場で颯爽と走る馬を間近に見る機会を得た。異次元の勢いで、私の目前を馬が横切って行った時の、あの新鮮な感覚は今なお色褪せない。大地を叩く蹄の音のみが響いてくると思いきや、鼻息の発する音が予想外の大きさだったのである。それまで、蹄の音だけを思い浮かべながら、走る馬を描いていた私は、とんでもない勘違いをしていたことに唖然としてしまった。むしろ、大きく開いた鼻の穴から勢いよく噴き出される息吹の方が、より強い音圧を誇っていたように思える。ウッドチップを高々と蹴り上げながら、次から次へと力強く坂路を駆け上がってくる彼らの姿を、心のスケッチブックに夢中で刻みつけていたことが、昨日のことのように思い出される。
ベッドで寝ていると、ピョンっと足元に乗っかってきたり、腕を押しのけてへばりついてきたり、動くことのない私の傍は居心地が良いのか、何匹もの猫たちが甘えてくる。
我が家では、最大で猫7匹・犬1匹が同居していた時期があったが、彼らが寄ってくることが煩わしいとか、邪魔でしようがないというわけではなく、むしろそういった状態を愉しんでいたように思える。餌をやれるわけでも、撫でてやれるでもない自分のところに、それでも依存するかのように集まってきてくれる彼らに、こちらのほうが何やら心のよりどころのようなものを見出していたのかもしれない。
私の筆に、生命を吹き込んでくれた彼らに、感謝の念は絶えない。

絵を描き始めたころは、まず、油絵具に慣れること、そして、対象をよく見ることの訓練として、静物を描くことが多かった。しかし、少しずつ要領がわかってくると、対象物を、ただキャンパスに写し取っていくだけの絵ではなく、心の奥に潜んでいる何かを描き込みたいと感じるようになっていた。今であれば、たとえ対象が静物であっても、そこに、メッセージを封入することは当たり前に可能なこととして考えられるのだが、当時の私には、無機質なものに思い入れを感じることは、ひどく無理なことのように思えたのである。
何が描きたいのか?
同程度の障がい者に比べて外出する機会が多い私ではあったが、それでも、家の中で過ごす時間が圧倒的に多かった。やはり、外に出るということは、それなりに特別なことであったのだろう。外に出た途端、何やら不思議な感覚に包まれるのである。
協会に所属することで、自身の絵が製品として世に送り出されるという喜びも得られるようになった。もちろん、自分の作品を採用したものがきちんと売れたのかどうかという厳しい評価もついて回るが、そういった緊張感を持った環境で制作することが、さらなる向上心へと繋がってくれた気がする。
人物画は苦手だ。
どれだけ似せることができたとしても、描き手の目が曇っていれば全くの別人になってしまう。間違った目で見ていたことが露呈する怖さを内包している。描く相手と正面から向き合い、その上で己の中身までさらけ出してしまうことを覚悟する必要があるのだ。そんな人物画は、自分の画力が足りないことを暴き出されてしまうようで、特別な事情がある場合以外は描くことを避けていた。
しかし、弟妹にこどもができてからの心の風向きは大きく変わる。遊ぶ相手をしてやれるでもない私のところに、どういうわけかくっつきたがる。ベッドの上のわずかなスペースに入り込んできたり、車いすに乗れば、膝の上にとやってくる。無邪気そのもの、文句なしに愛らしい。そんな彼らを見ているうち、描かずにはいられなくなってしまった。
要するに、絵というものは描きたくて描くものなのだ。どんな題材であれ、心が突き動かされれば、自ずとキャンバスに向かうことになるのである。
そんな、最も初歩的で、最も基本的なことを、まだ幼いこどもたちに教えてもらったような気がする。