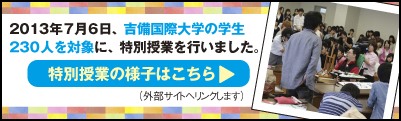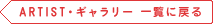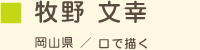
1966年1月富山県生まれ。
高校2年生の夏、水泳の練習に失敗して頭を強打し頚椎を損傷。以来、首から下全身がマヒしていた。
15ヶ月の入院後、車椅子で元の普通高校に復帰、級友の助けを借りて見事に卒業した。
卒業後、リハビリの先生に勧められ口で絵を描き始めた。職業画家のもとで、毎日長時間の修練を重ね、4ヶ月で描けるようになった。絵は、一人では何ひとつ出来ない自分が唯一輝くことのできる場所だと言った。
さらに書道にも情熱を傾け、2004年に教授免許(五段)を取得した。
絵画制作の傍ら、同協会の巡回展会場にて実演、また、地元の学校や公民館などでの講演活動を行っていた。
2017年6月没。


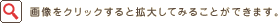
「描くこと」と「生きること」
何もすることが見つけられず、ただ時間をやり過ごすだけの日々。漠然とした焦燥感に追いかけられるなか、リハビリの先生から勧められて「描くこと」を始めました。
それは、大きく抜け落ちていた何かを補完し、やがて、「生きること」と同等の意味を持つものとなりました。「描くこと」と出会えたことで、「死んでいないだけ」の人生が「確かに生きている」と言えるものへと昇華したのです。
協会に所属することで、自身の絵が製品として世に送り出されるという喜びも得られるようになりました。もちろん、自分の作品を採用したものが、きちんと売れたのかどうかという厳しい評価もついて回りますが、そういった緊張感を持った環境で制作することが、さらなる向上心に繋がってくれているのです。
時には、制作に没頭するあまりに体調を崩してしまうこともあります。しかし、「生きること」への渇望は、それにも増して、私を「描くこと」へと力強く誘(いざな)うのです。
世の中には、自分の存在意義を見出すことができないまま暗い闇へと迷い込んでしまい、明日への希望を失いかけてしまっている方々が、少なからずいることと思います。私が、「描くこと」と出会い「生きること」の意義を見つけられたように、微力ながらも、私達の絵画がそういった方々の明日への光を見つけるための、きっかけの一つになることが出来るならと願わずにはいられません。
これからも「生きること」を続けていくにためは、大勢の人たちの善意の支えに頼らなければならいのである、ということを決して忘れる事はないでしょう。
ご購入くださった皆様に喜んでいただけるように、少しでも良い作品を創り出すため、仲間たちとともに切磋琢磨し続けたいと思っています。
今後とも、宜しくお願いいたします。
上記は、牧野 文幸が2012年に絵に対する思いを描いた文章です。
<略歴追記>
平成 8年 倉敷市文化振興財団に作品を寄贈。倉敷美観地区内にある倉敷館観光案内所に展示される。
平成13年 日本習字教育財団・成人部(漢字部)に入会
平成16年 同財団の教授免状を取得
平成23年 倉敷加計美術館にて個展「生きるよろこび」を開催
展示作品から5点選び、協会出版社が絵はがきを製作しミュージアムショップで販売
売り上げの一部を、東日本大震災の義援金に寄付
平成23年 児島 虎次郎 生誕130周年記念展 「虎次郎 素描(デッサン)のすゝめ」タイトルロゴを制作
平成23年・24年 医学書院 理学療法ジャーナル/「とびら」欄の掲載作品を担当
平成24年 東日本大震災 ダイレクトチャリティ展 ポスター用副題ロゴ・一本松挿絵を制作
平成25年 牧野文幸展 生きるよろこび 「縁(えにし)」を開催
平成27年 牧野文幸追悼展 「生きるよろこび」を開催